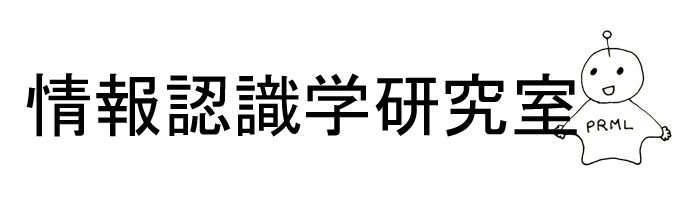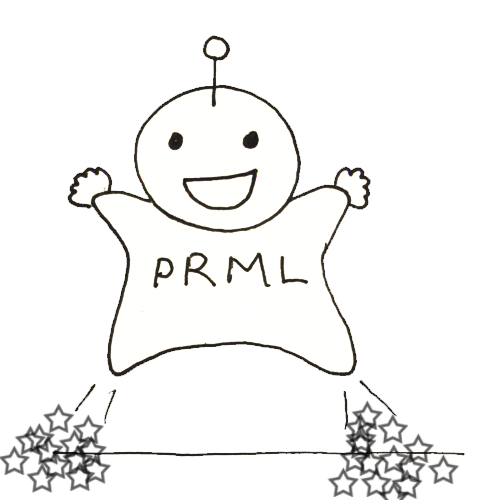教授の工藤は2023年度で退職します。
ご挨拶
情報認識学研究室に興味をもってくださってありがとうございます。 以下のQ&Aは、皆さんが知りたいと思われることについて、研究室の先輩がこたえてくれたものです。研究室選びの参考にしてください。
研究室紹介ファイル(教員作成版)は研究室紹介2021.pdfをご覧ください。(2021.9.28)
研究室での生活について詳しく知りたい方はこちらもご覧ください。
研究室の雰囲気は?
和やか・穏やかで、わいわいやるのが好きです。まじめで、やさしい先輩、面白い先輩が多いと思います。
添削や、研究発表の指導では、先輩達からの鋭い(鋭すぎる)指摘がたくさん来ます。ゼミでは先生方の質問に言葉を詰まらせることもあります。あんまりにもビシッと指摘され過ぎて「しょぼーん」となってしまうこともあります。でもこれらは研究を進める上でとても参考になりますし、確実にスキルが向上します。
研究はどのように進めるのですか?
研究室配属後、始めに3年後期および4年前期では、基礎的な知識に関するゼミを行い、ここでしっかりと基礎固めを行います。(ここでの訓練がボディブローのように後でじわじわ効いてきます。)主に、輪講形式で1冊の本を読みますが、内容を理解しているかどうかに関して、特に、概念を図を用いて説明するよう求められます。これが、非常にきついのですが、式の意味を捕らえ、自分で式を立て、論理を展開することの訓練は、後の卒業研究のために非常に役に立ちます。
4年生になってからは、自分の読んだ論文や自分の進めている研究に関して発表を行い、(週二回、持ち回り)、各研究チーム主催のゼミを参加し、それらの中で揉まれながら、課題を決め、方向性を逐次訂正しつつ、卒論を仕上げていきます(情報認識学研究室は論文の〆切が少し早いです)。研究をうまく進めることが出来るかどうか不安な人も多いと思いますが、多くの先輩方が懇切丁寧に示唆、協力してくれますので、安心しても構わないと思います。実際、達成可能な課題を進められるように、各自の進捗状況を見ながら、これらの発表会およびゼミの中で、こまやかな方向修正が行われるので、ささやかであっても、何とか各自の独自性を出すことはできます。達成感は味わえると言えます。(どんなにささいでも)。
就職はどうなんでしょうか?
現在、多くの学生が大学院を希望しますが、勿論、学部で就職することはできますし、今年度の状況を見ますと、ほぼ希望通りに就職が決まるようです。その点に関しては安心して良いでしょう。
大学院へ進む方がいいの?
産業界へ就職する際でも学部卒で十分ではなくなって来ているように思います。かなり前までは、「研究部門、研究職につくなら最低修士」という図式があったように思いますが、これがだんだん、「研究部門、研究職につくなら博士」となり、現在では修士号を持っていても、必ずしも、研究部門への希望は難しくなっていると聞いています。言い換えれば、「情報工学の素養は修士ぐらい出ていないとつかない」と産業界が思っている気がします。大学院進学には四つの意義があると思います。
- 産業界の期待する程度の素養を身につけて就職したい。
- 将来、研究部門、研究職につきたい。
- 自分を見つめ直し、自分の可能性を検討する時間が欲しい。(別名、モラトリアム)
- 自分なりのものをわずかでもいいから造り出して見たい。
ただし、大学院はそんなに甘くはありません。4. が修了の必要条件です。何か、「自分で造り出してやろう」、という気構えが全くないようであれば、進学を勧めません。大学院は、自分で、課題を見つけ、問題点を明らかにし、その問題点の解決のために新しい創造を行い、それがどの程度の貢献であるかを客観的に評価できる、力をつけるところです。